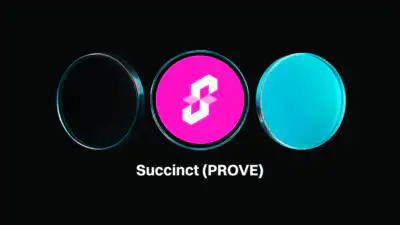ゴーレム(Golem / GLM)とは何か、その仕組みについて
分散型ネットワークにおける計算能力のレンタルおよび支払いを、より簡便かつ非中央集権的に実現する目的で開発されたのが、イーサリアムネットワーク上で初期に登場したプロジェクトの一つである「Golem」である。
Golemは、2016年にGolem Factoryによって提唱され、約2年後にローンチされた。世界第2位のブロックチェーンネットワーク上で、オンデマンド型の計算リソースを提供するピア・ツー・ピア(P2P)型のマーケットプレイスを構築している。
本プロジェクトの主目的は、十分な計算能力を持たないユーザーに対し、さまざまな用途のプロジェクトに必要なコンピューティングパワーを提供することである。
Golemは、中央集権型モデルと比較し、分散型P2Pマーケットの可能性を最大限に引き出している。ブロックチェーン技術を活用することで、支払い、レンタル、計算リソースの利用方法を利用者自身が管理できるようにし、真の意味での民主性と非中央集権性を実現するエコシステムを形成している。人工知能(AI)や暗号資産マイニングをはじめとする多様な分野で、ユーザーは計算能力を売買できる環境が整えられている。
GLM(ゴーレム)の概要
GLM(ゴーレム)は、ブロックチェーンを基盤とするソフトウェアであり、ユーザーが計算能力を売買できるプラットフォームを提供する。用途は、人工知能、暗号資産マイニング、CGIレンダリング、その他大規模な計算処理を要する分野など多岐にわたる。
GLM(ゴーレム)は従来型クラウドサービスの分散型代替手段として位置付けられ、中央管理者や第三者に依存しないユーザー主導型のモデルを実現している。
余剰の計算能力を有するユーザーは、それをリソース不足のユーザーに販売し、対価としてGLMトークンを受け取る。支払う側のユーザー(リクエスター)は、自らのプロジェクト実行に必要な計算能力の量に応じて支払いを行う仕組みである。
GLM(ゴーレム)は、リクエスターからの要求を小規模なタスクに分割し、複数の提供者(プロバイダー)から計算能力を集約することで、スケーラブルなP2P型マーケットを形成している。GLMはこのネットワークのユーティリティトークンであり、価値の保存および取引の媒体として機能する。
GLM(ゴーレム)の仕組み
GLM(ゴーレム)は、リクエスターとプロバイダーを効率的にマッチングさせることで動作する。
計算能力を購入するユーザーは「リクエスター」、提供するユーザーは「プロバイダー」と呼ばれる。
リクエスターがタスクを作成すると、Golemシステムはその要求を検証し、適切なプロバイダーを自動的に割り当てる。要求されたタスクは細分化され、複数のノードで並列的に実行される。
例えば、リクエスターがCGIレンダリングなど大規模な計算処理を必要とする場合、従来のクラウドサービスに依存するとコストや処理時間がかかるが、Golemではタスクを分割してP2Pネットワーク上の複数ノードに分配することで、より迅速かつ低コストで処理を完了できる。
リクエスターはテンプレート化されたタスクを利用し、Golemネットワーク上で実行を依頼する。完了後は、支払いがスマートコントラクトを通じてプロバイダーに送られる。
開発者および歴史
GLM(ゴーレム)は、Aleksandra Skrzypczak、Andrzej Regulski、Julian Zawistowski、Piotr Janiukの4名によって共同設立されたGolem Factoryによって開発された。
同社は2016年に設立され、2018年にGolemネットワークを正式にローンチした。
当初の目的は、中央機関の関与なしに大規模プロジェクトに必要な計算リソースを提供することにあった。2016年の資金調達では、ETH建てで約860万ドルを獲得している。
当初トークンはGNTと呼ばれていたが、Ethereumのレイヤー2対応に伴いERC-20規格が採用され、2020年11月より1:1の比率でGLMへの移行が開始された。
GLM(ゴーレム)の特徴
GLM(ゴーレム)は、リクエスターのタスクを分割して処理することで、クラウド計算サービスを自動化・分散化し、コスト効率を大幅に向上させている。
従来の中央集権的クラウドサービスとは異なり、Golemでは市場のコントロールがユーザー自身の手に委ねられており、プロバイダーは直接報酬を受け取る。
この仕組みにより、ユーザーは自らの計算能力を販売してGLM報酬を得ることが可能となり、リクエスターは低コストで必要なリソースを確保できる。
GLM(ゴーレム)の価値
GLM(ゴーレム)の価値は、その実用性、技術力、ネットワーク設計に基づいている。
分散型で安全なP2P市場を構築するためのテクノロジー自体がGolemの内在的価値を形成しており、クラウドサービスコストの削減や計算効率化という観点からも大きな意義を持つ。
ただし、GLMの市場価値は暗号資産特有の価格変動に影響されやすく、常に実用価値と市場価格が一致するわけではない。
供給量
GLM(ゴーレム)の発行上限は10億枚であり、すべてのGLMトークンはすでに発行済みである。
供給量が固定されているため、新規発行によるインフレーションは起こらない。
流通中のGLMの総量に市場価格を乗じたものが時価総額となり、暗号資産市場におけるGolemの順位およびシェアを示す指標となる。
技術的構成
GLM(ゴーレム)のアーキテクチャは、リクエスターによるタスクテンプレートをもとに動作する。各リクエストには、実行すべきソースコード、タスクを分割してノードに送信する命令、および検証方法が含まれる。
また、トランザクションフレームワークおよびアプリケーションレジストリが統合されており、開発者は多様なツールやテンプレートを展開できる。アプリケーションレジストリはEthereum上のスマートコントラクトとして機能し、Google Playのような役割を果たしている。
ネットワークセキュリティ
GLM(ゴーレム)は、悪意あるノードを排除するためのレピュテーションシステムを採用している。
タスクが完了するたびにユーザーの評価が行われ、信頼スコアが形成される。
また、Ethereumネットワークのコンセンサスメカニズムに依存しており、Proof of Workによって安全性と機能性が担保されている。Ethereum 2.0の完全移行後は、Proof of Stakeによりセキュリティがさらに強化される見通しである。
利用方法
GLM(ゴーレム)の最終的な目標は、Web3.0時代におけるデータ共有の新しい基盤を提供することである。
ユーザーは、計算リソースを売買するだけでなく、開発者としてツールやテンプレートを展開し、市場を拡張できる。
GLMトークンは報酬システムの中核を担い、主要な支払い手段および価値保存手段として機能する。また、暗号資産市場において他の通貨との取引も可能である。
ウォレットの選択
GLMはERC-20トークンであるため、Ethereum対応ウォレットであれば保管可能である。
保管目的や資産規模に応じて以下の選択肢が存在する。
- ハードウェアウォレット(コールドウォレット)
LedgerやTrezorなどのデバイスでオフライン保管を行う最も安全な方法。高度な知識が必要だが、大口保有者に最適。 - ソフトウェアウォレット
モバイルやデスクトップで利用でき、無料で利便性が高い。カストディ型と非カストディ型があり、後者は秘密鍵を自身で管理する。 - オンラインウォレット(ウェブウォレット)
ブラウザ経由で簡単にアクセスできるが、セキュリティリスクが比較的高い。信頼性の高い運営企業を選定することが重要である。
okwallet.jpは、安全性と利便性を両立したGLM保管および取引プラットフォームを提供しており、エンタープライズ級のセキュリティを実現している。
コンセンサスと供給構造
GLM(ゴーレム)はすべてのトークンが事前に発行済みであり、マイニングやステーキングによる新規生成は行われない。
Ethereumのコンセンサスを基盤としつつ、GLM報酬およびレピュテーション制度によって経済的安定性を維持している。
この仕組みにより、Golemネットワークは高い耐障害性と透明性を両立している。
結論
GLM(ゴーレム)ネットワークは、計算リソースの売買において最も信頼性の高いP2Pマーケットの一つとして位置付けられている。開発チームは、今後さらにアプリケーションの拡張と機能追加を進め、将来の計算需要に対応することを目指している。
同時に、Golemは分散型インターネットの中核的存在となり、余剰計算能力を持つ人々に新たな収益機会を提供することで、より公正で効率的なデジタル社会の実現を目指している。
暗号資産の新しい時代へ、今すぐGolemと共に歩み始めよう。